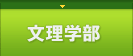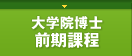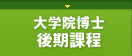検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

社会調査実習
| 科目名 | 社会調査実習 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 社会調査実習 | ||||
| 教員名 | 松橋 達矢 | ||||
| 単位数 | 4 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 「新線/新駅」設置に伴う 都市地域社会変動に関する研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 「社会調査士コース」の3年次必修科目である。社会調査士資格認定機構の「社会調査士」資格を取得するためには、社会調査の全プロセスの経験を通して学ぶ「社会調査実習科目」の履修が義務づけられている。この授業では、先行研究レビューから、問題意識の明確化、調査の企画、実施、エディティング、コーディング、データ入力、分析、考察、報告書の刊行に至るまでの社会調査の一連の作業を全て体験し、量的調査のノウハウを身につける事を目標とする。 |
| 授業の方法 | 調査の作業プロセスを授業の進行に伴って進める。仮説や分析枠組みの解説と議論から始まり、操作化、質問項目と選択肢の作成、レイアウトへの配慮などの調査票作成、それから宛名ラベルの作成、発送用・返信用封筒の作成、挨拶文、督促兼お礼状の作成、データ回収作業、エディティング、コーディング、データ入力とクリーニング作業、分析とレポート作成といった一連の過程を進める。時間が限られているため、授業外の時間も有効に使いながら、効率的に進める必要がある。 |
| 履修条件 | 原則として、2年時にエントリーをして、履修を認められた学生。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 先行研究のフォローならびに過去調査データの再分析(1) |
| 3 | 先行研究のフォローならびに過去調査データの再分析(2) |
| 4 | 調査の企画・設計(1)(調査地・対象の概況把握) |
| 5 | 調査の企画・設計(2)(サンプリング&データ分析&アウトプットの方法等確認) |
| 6 | 仮説の構築と質問項目の検討(1) |
| 7 | 仮説の構築と質問項目の検討(2) |
| 8 | 仮説の構築と質問項目の検討(3) |
| 9 | 調査票等の作成 &プリテスト |
| 10 | 調査実施要領の作成&調査倫理の確認 |
| 11 | 調査作業実施(1) |
| 12 | 調査作業実施(2) |
| 13 | 調査進捗状況共有とエディティング&コーディング方針の確認 |
| 14 | 課外学習 |
| 15 | エディティング&コーディング&転記作業(1) |
| 16 | エディティング&コーディング&転記作業(2) |
| 17 | データ入力&クリーニング(1) |
| 18 | データ入力&クリーニング(2) |
| 19 | データ集計(1)(単純集計&基礎統計量算出) |
| 20 | データ集計(2)(単純集計&基礎統計量算出) |
| 21 | データ分析(1)(2変数間の関連性&関連係数) |
| 22 | データ分析(2)(2変数間の関連性&関連係数) |
| 23 | データ分析(3)(2変数間の関連性&関連係数) |
| 24 | データ分析(4)(多変量解析ほか) |
| 25 | データ分析(5)(時点間・地域間比較) |
| 26 | 分析結果の相互報告と討論を通じた分析結果考察(1) |
| 27 | 分析結果の相互報告と討論を通じた分析結果考察(2) |
| 28 | 報告書作成にむけて |
| 29 | 課外学習 |
| 30 | 合同成果報告会 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 大谷信介ほか 『新・社会調査へのアプローチ』 ミネルヴァ書房 2013年 第1版 |
| 参考書 | 授業内で適宜指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、レポート(40%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 授業開講時に指示する。 |
| 備考 | 社会調査は、現場の方々のご厚意により成立しているため、正規の授業時間外にも、相当な時間とエネルギーを費やして諸課題に取り組むことになります。 |