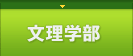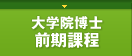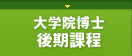検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

社会学演習
| 科目名 | 社会学演習 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 社会学演習 | ||||
| 教員名 | 松崎 茂 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 環境社会学の基本的な考え方を理解する。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 環境社会学の基本的な考え方を学習し,人間と自然環境との関係について理解を深める。 |
| 授業の方法 | 前期は,テキストの輪読を通じて,基本的な知識を学ぶことを目的とする。後期は,指定したテーマによるグループ発表,および関心があるテーマについての個人発表を行う。各自のテーマによる研究レポート2回(夏休み,冬休み),指定図書の読書レポート2回(前期,後期)。 |
| 履修条件 | 受講許可を得た学生 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 前期は,テキストの輪読を通じて,環境問題と環境社会学について理解する。後期は,関心のあるテーマによるグループ発表および個人発表 を行う。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 前期ガイダンス:授業の進め方について |
| 2 | 社会学における環境問題の位置づけ |
| 3 | 人間社会と環境を考える(環境問題の発見,環境社会学の成立と展開など) |
| 4 | 自然保護を考える(世界遺産,野生生物保護など) |
| 5 | 身近な自然を考える(河川および森林の保全,コモンズなど) |
| 6 | 生活と水を考える(琵琶湖水質問題,河川の近代化など) |
| 7 | 農と食を考える(有機農業運動,農村と地域づくりなど) |
| 8 | ゴミ問題を考える(共有地の悲劇,リサイクル運動など) |
| 9 | 環境NPO/NGO・ボランティア・市民活動を考える(環境NPOとコミュニティビジネスなど) |
| 10 | まちづくり/地域づくりと環境を考える(まちづくり論,自治体の環境政策など) |
| 11 | 歴史的環境と景観を考える(歴史的環境,景観の保全など) |
| 12 | 公害・差別・リスクを考える(公害問題,水俣病など) |
| 13 | 開発と資源・エネルギー問題を考える(大規模開発,原発問題など) |
| 14 | 地球環境問題を考える(温暖化対策,エネルギー政策など) |
| 15 | 前期まとめ |
| 16 | 後期ガイダンス:発表の進め方について |
| 17 | グループ発表① |
| 18 | グループ発表② |
| 19 | グループ発表③ |
| 20 | グループ発表④ |
| 21 | ディベート① |
| 22 | ディベート② |
| 23 | ディベート③ |
| 24 | ディベート④ |
| 25 | 個人発表① |
| 26 | 個人発表② |
| 27 | 個人発表③ |
| 28 | 個人発表⑤ |
| 29 | 個人発表⑥ |
| 30 | 後期まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 鳥越皓之ほか 『よくわかる環境社会学』 ミネルヴァ書房 2009年 第1版 教科書を必ず購入すること。 |
| 参考書 | 鬼頭秀一 『自然保護を問いなおす』 筑摩書房 1996年 第1版 詳細については,開講時に指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(20%)、授業参画度(60%) 出席(3/4以上が必要),指定されたレポートの提出,および課題・発表が必要とされる。 |
| オフィスアワー | 開講時に指示する。 |
| 備考 | 前期は授業と併せて,演習に必要な技術の習得を行う(PC操作方法,レジュメ作成,プレゼンテーション用資料の作成など)。 |