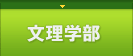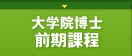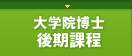検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

上代文学講義2
| 科目名 | 上代文学講義2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 梶川 信行 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 国文学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 大伴家持の歌を読む |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 今年は大伴家持生誕1300年と言われ、家持ゆかりの地ではさまざまな記念行事が行われている。それを機会に、本講義でも大伴家持の歌々をじっくり読み込んでみたいと思う。家持は古来、『万葉集』の編纂者に擬せられている。歌に関するさまざまな資料が家持の手元に集められたことが窺えるが、それもあって家持は、初期万葉以来の歌の伝統を集約したところに位置づけられる。ヤマトウタの歴史をどう受け継いで家持の歌の世界が成り立ったのか。本講義では、家持の作品を読み進めることを通して、古代和歌の成熟過程を見据えてみたいと思う。 |
| 授業の方法 | 毎時間プロジェクタを使用し、できるだけ多くの画像を見せつつ講義をすることで、理解が深められるようにするつもりである。また、授業中に小さな課題を与えることも考えている。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習等の教材については、Blackboardに掲載する。また、復習のため、その日の授業のもっとも重要な教材もBlackboardに載せておく。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス 『万葉集』における大伴家持の位相 |
| 2 | 青春時代の家持――大伴坂上郎女の影響 |
| 3 | 青年たちの宴席――社交の歌への眼覚め |
| 4 | 亡妾悲傷歌――亡妻挽歌の系譜 |
| 5 | 伊勢行幸への従駕――従駕歌人の系譜 |
| 6 | 恭仁京の日々――宮廷歌人への憧憬1 |
| 7 | 安積皇子への挽歌――宮廷歌人への憧憬2 |
| 8 | 雪の肆宴――士大夫の自覚 |
| 9 | 越中への下向――夷における生活詠 |
| 10 | 二上山の賦――国土讃美の歌の系譜 |
| 11 | 田辺福麻呂の越中来訪――社交の歌の成熟 |
| 12 | 配下の人々との交流――夷における雅 |
| 13 | 越中秀吟――新たな歌の世界へ |
| 14 | 防人歌の収集――意識された氏族の伝統 |
| 15 | 因幡国庁の正月 まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 森淳司 『訳文万葉集』 笠間書院 2007年 信頼性の高いテキストならば、指定のもの以外でも構わないが、本文に違いのあることを留意しておくこと。 |
| 参考書 | 授業中、適宜指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(70%)、授業参画度(30%) 授業の内容を反映しないレポート、参考文献を丸写ししたレポートは、評価の対象としない。 また、提出期限を過ぎたレポートは受理しない。 なお、レポートの書き方、評価の方法などに関するプリントを11月頃に配布する予定である。 |
| オフィスアワー | 月・木・金。時間は開講時に伝える。 |