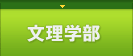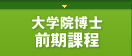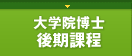検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

ドイツ語5 (他学科用)
| 令和2年度以降入学者 | ドイツ語5 (他学科用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度以前入学者 | ドイツ語基礎3 | ||||
| 教員名 | 高宮純子 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 2~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 外国語科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業の形態 | 同時双⽅向型授業(Zoomによるライブ中継)と課題研究(BlackBoard を通じた資料配信)の組み合わせによって授業を行う。 Blackboard コースID: 20210844, コース名:2021ドイツ語5/ドイツ語基礎3(高宮純子・前・月4)に登録しておくこと。 |
|---|---|
| 授業概要 | 既習の文法や知識を総合的に復習し、反復練習によって基礎を固め、新しい文法事項や語彙を少しずつ加えていくことで読解力と表現力を伸ばしていく。さまざまなドイツの習慣や社会制度についてのテキストを購読し分析することで、ドイツ人の考え方を把握し、ドイツ語運用に必要な論理的思考能力を身につける。ドイツ人と日本人の思考や感覚を比較することで、その相違をドイツ語で表現できるようにする。 |
| 授業のねらい・到達目標 | これまでに学んだ文法事項や語彙、表現を丁寧に確認していきながら、必要な知識を補足して基礎文法を確かなものにする。初級レベルの基礎固めをするとともに、中級レベルの文法事項も学ぶことで、自分の意見を伝えたり簡単な説明を可能にする。 各課毎に「ドイツ語を学びながらドイツ人の考え方を知ること」をテーマとしたドイツ語テキストを購読し、議論と分析をする。ドイツ語圏の社会や文化、考え方を把握していき、ドイツ文化の様相を説明できるようになる。(A2-1)(A3-1) この科目は文理学部(学士(文学)のディプロマポリシーDP2,DP3およびカリキュラムポリシーCP2,CP3に対応している。 |
| 授業の方法 | 授業の形式「演習」 (1)基本的に指定の教科書をもとに進めるが、その他の文法事項やドイツ語表現も随時補足する。その資料はこちらで用意する。2回で一つの課を進める。 (2)双方向型授業としてZoomを利用する。複数人が同時に書き込めるオンラインテキストエディタとZoomのブレイクアウトルームを使用し、メインルームでの講義、ペアワーク、グループワークなどで双方向の授業を行う。 (3)それぞれが発言しやすいクラスをつくり、間違えを恐れずに発言やボードへ書き込みを行う。 (4)各回の最後に指示された教科書の課題、あるいはこちらで用意した練習問題や作文課題などを解き、提出の義務がある回には、期限までに提出すること。解答は、期日締め切り後に配信する。また、翌週の授業で解説をする。 (5)Blackboardのメールを通して質問を受け付ける。 (6)到達度確認として、Lektion2とLektion4終了後に試験を行う。 2回の試験はそれぞれに返却し、翌週に解説をおこなう。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス 【同時双方向型】 Zoomの操作確認、学期の授業内容、授業の目的と方法についての説明をする。ドイツ語のレベルを確認するとともに、それぞれのドイツ語を学ぶ意義について考える。 【事前学習】シラバスを確認すること。Zoomを事前に試してみること。 (0.5時間) 【事後学習】授業で配布されたアンケートに答えて期限内に提出すること。 (0.5時間) |
| 2 |
発音の確認、既習の文法事項の復習【同時双方向型】 発音の規則を再確認するとともに、A1レベル内の重要な文法事項を復習する。この文法事項の復習は、ガイダンス時のレベルの確認をもとに行われる。 【事前学習】既習の文法事項と表現を再確認し不明な点があれば用意しておくと。 (0.5時間) 【事後学習】指示された練習問題を解いてくること。また、授業内での文法規則で不明な点を確認して次の時間までに用意しておくこと (0.5時間) |
| 3 |
Lektion 1 : パーティーをするのは祝ってもらう人【同時双方向型】 不定関係代名詞、分離動詞 【事前学習】教科書付属の音声をききながら教科書6ページのテキストを一読し、単語を調べておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】テキストのドイツ語訳をもう一度確認し、授業で新たに得た知識をまとめること。授業内で指定された「不定関係代名詞」「分離動詞」の問題を解いてくること。 (0.5時間) |
| 4 |
Lektion 1 : パーティーをするのは祝ってもらう人【同時双方向型】 文法練習と応用 序数、前置詞、不規則変化動詞 【事前学習】教科書10−12ページの音声をきいておくこと。単語を調べておくこと。不明点を明らかにすること。 (0.5時間) 【事後学習】「不規則変化動詞」「前置詞」に関する練習問題を解き、課題として期限内に提出すること。 (0.5時間) |
| 5 |
Lektion 2 : 20歳過ぎれば親もとを離れる【同時双方向型】 テキスト購読 形容詞の格変化、並列の接続詞 【事前学習】教科書14ページの単語の意味を調べておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】授業で扱ったテキストのドイツ語訳を確認すること。授業内で指示された練習問題を解いてくること。 (0.5時間) |
| 6 |
Lektion 2:20歳過ぎれば親もとを離れる」【同時双方向型】 文法練習と応用 方向を表す前置詞、人称代名詞の合体、ドイツ語の造語法 【事前学習】Lektion1-2を復習しておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】テキストのドイツ語訳をもう一度確認して不明点を明らかにすること。 (0.5時間) |
| 7 |
Lektion 3 : 教室で手を挙げないと原点!【同時双方向型】 テキスト購読 名詞の複数形、zu不定詞句 【事前学習】教科書の20ページを訳してくること。 (0.5時間) 【事後学習】返却されたオンデマンド試験の結果を分析し、間違いがあった文法事項や語彙を復習し、必要であれば反復練習をしておくこと。(A−8) (0.5時間) |
| 8 |
Lektion 3:教室で手を挙げないと原点!【同時双方向型】 文法練習と応用 対になる言葉、zu不定詞句 【事前学習】教科書24−25ページの不明な単語を調べてくる。 (0.5時間) 【事後学習】授業内で指示された「zu不定詞句」に関する練習問題を解き、課題として期限内に提出すること。 (0.5時間) |
| 9 |
Lektion 4 : 2回失格だと失格! 【同時双方向型】 テキスト購読 「〜のひとつ」の表現、話法の助動詞 【事前学習】教科書26ページのテキストを訳してくること。テキストの音声を確認しておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】「話法の助動詞」に関連する練習問題を解き、課題として期限内に提出すること。 (0.5時間) |
| 10 |
Lektion 4 : 2回失格だと失格!【同時双方向型】 文法練習と応用 話法の助動詞、様々な動詞の意味と使い方 【事前学習】試験に関連する語彙のリストを確認して、不明な単語を訳しておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】配布資料の「試験」に関連した練習問題を解いてくること。 (0.5時間) |
| 11 |
Lektion 5 : 事故死傷者の氏名公表はご法度!【同時双方向型】 テキスト購読 受動態 【事前学習】教科書32ページのテキストを訳してくること。音声を確認しておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】指示された「受動態」の練習問題を解いて、課題として期日までに提出すること。 (0.5時間) |
| 12 |
Lektion 5 : 事故死傷者の氏名公表はご法度!【同時双方向型】 形容詞の名詞化 【事前学習】教科書Lektion5内の指示されたページの単語の意味を調べてくる。 (0.5時間) 【事後学習】教科書36ページの設問7の問題を解いて訳してくること。この課題は期日までに提出すること。 (0.5時間) |
| 13 |
典型的なドイツ人?ドイツ人のメンタリティー【同時双方向型】 テキスト購読、議論と分析 ドイツ語の動画と記事をもとに、ドイツ人の典型的な特徴についてそれぞれ意見を出し合い、ドイツで生活する際に必要な考え方や心理的態度を考える。 【事前学習】事前に指示された動画を視聴し、ドイツ語の記事を一読しておくこと。 (0.5時間) 【事後学習】新しく学んだ語彙と表現を整理してまとめること。 (0.5時間) |
| 14 |
期末試験とその解説【課題研究】 Lektion1-5で学習したテーマや文法事項の確認。授業開始時に、試験問題のデータを配る。その問題に回答し、時間内に提出すること。(90分) 【事前学習】Lektion1-5をもう一度振り返り、文法事項とテーマを整理して総合的に復習しておくこと (0.5時間) 【事後学習】不明点や難易度の高い問題や文法を振り返り、繰り返し復習すること。 (0.5時間) |
| 15 |
まとめ 【同時双方向型】 これまで学んだ知識を総合的に整理し、理解度を確認する。それぞれが到達度を確認するとともに、全体を通して総評を行い、必要に応じて補足説明する(A8-2) 【事前学習】前期で学習した文法事項と単語の確認し、不明な点を明らかにしてくること。 (0.5時間) 【事後学習】それぞれの分析をもとに、必要箇所を復習しておくこと。 (0.5時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 『ドイツ人を知る9章+1 (大谷弘道 )』 三修社 2007年 |
| 参考書 | 同時双方向の授業では、教科書のデータの他に、オンライン上でインターネット辞書・資料・動画を使用する。 (Duden,DWDS, Deutsche Welle など) インターネットの辞書・資料等の使い方と注意点は授業内で説明する 日本語での参考書として「必携ドイツ文法総まとめ」を紹介するが、購入は必須ではない。 その他参考書は授業で随時紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(60%)、授業参画度:授業での発言やリアクションペーパー(40%) 積極的な発言や授業態度は高く評価する。 |
| オフィスアワー | Blackbordを通じて行う。またはメールで対応する。 |