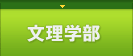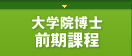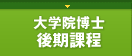検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

書道科教育法Ⅰ
| 令和元年度以降入学者 | 書道科教育法Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年度以前入学者 | 書道科教育法Ⅰ | ||||
| 教員名 | 山本まり子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業の形態 | 毎回、Zoomを使用し、同時双方向による授業を行う。適宜、オンデマンド教材を取り入れる。 オンライン授業の開始時刻は時間割通り、13時。第1回目の授業からZoomを使用する(その実施のためのURLはBlackboard上、告知する)。第1回目までにBlackboardへの登録を済ませておくこと。 Blackboard コースID:20213516 |
|---|---|
| 授業概要 | 『学習指導要領』に示された芸術科書道の「目標」・「内容」の把握と適切な評価方法の修得を目指す。授業担当者の教職経験(中学校国語科「書写」・高等学校芸術科「書道」)を活かして下記目標の達成に努める。 |
| 授業のねらい・到達目標 | 1)『学習指導要領』改訂の変遷、及び同書における書道科の「目標」・「内容」の要点、適切な評価方法について説明できる。 2)現在の教育現場の実状を踏まえた上で、書写・書道教育に求められている指導内容・方法の在り方について理解し、自分の考えを持つことができる。 3)アクティブ・ラーニングについて理解し、それを取り入れた授業づくりの視点を持つことができる。 |
| 授業の方法 | 授業の形式:【講義】・【実技】・【研究】 必要事項について説明する。その後、実技(毛筆・硬筆)・レポート作成などの実践へと進める。 指定するGoogleDriveを活用する(データの容量の都合上、Blackboardによる教材の配信は原則、行わない)。 教科書(冊子体)に加え、GoogleDrive内に収めるデータ(映像・音声・資料)、本授業用HP内に収めるデータを活用する。それらのURLは個別にE-mailで告知する。 受講生作成の成果物へのフィードバックはE-mailによって行う。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
今後の授業の進め方、本授業において使用する教材の配信方法等に関する説明を行い、受講生からの質問を受け付ける。その後、ガイダンス(授業概要・到達目標・授業の方法、及び本授業に関する評価基準について補足説明)を行う。
【事前学習】シラバスの事前確認を行う。文部科学省HP上、『中学校学習指導要領』「国語」(平成29年)、『高等学校学習指導要領』「書道」(平成30年)の部分を通読しておく。 (2時間) 【事後学習】シラバスの再確認。『学習指導要領』中学「書写」・高校「書道」記載内容の再読。 (2時間) |
| 2 |
『学習指導要領』中学「書写」・高校「書道」記載の「目標」・「内容」について概説する。
【事前学習】文部科学省HPから『高等学校学習指導要領解説 総則編』(平成30年)P1~10記載の『学習指導要領』改訂の経緯及び基本方針について要点をおさえておく。 (2時間) 【事後学習】高校「書道」記載の「目標」・「内容」に関する要点をノートに整理しておく。 (2時間) |
| 3 |
高校「書道」における評価の観点、評価規準について概説する。
【事前学習】『高等学校学習指導要領解説 芸術編』の「評価」について内容確認を行う。 (2時間) 【事後学習】高校「書道」における評価の観点、評価規準について授業中、指摘する事例をもとに自身の考えをまとめる。 (2時間) |
| 4 |
中学「書写」の内容と高校「書道」との連関に関する事項について、受講生に対して質問する。その後、その指導の重要性について解説する。特に個々の文字については具体例を挙げながら詳説する(オンデマンド①)。
【事前学習】中学「書写」の内容と高校「書道」との連関に関することをノートに書き出す(第3回目の授業中、その内容について予告する)。 (2時間) 【事後学習】中学「書写」の内容と高校「書道」との連関について、授業中、取り上げた個々の文字を中心に整理し、指定の書式によりその類例を書き出しておく(次回の授業中、その提出を求める)。 (2時間) |
| 5 |
中学「書写」と高校「書道」との連関に関することを受講生に対して質問する。その後、その指導の重要性について解説する(オンデマンド②)。
【事前学習】第4回目と同様、中学「書写」と高校「書道」との内容的隔たりに関することをノートに書き出す(第4回目の授業中、それについて予告する)。 (2時間) 【事後学習】中学「書写」と高校「書道」との相違について、授業中、取り上げた個々の文字を中心に整理し、その類例を書き出しておく(後日、その提出を求める予定)。 (2時間) |
| 6 |
中学「書写」と高校「書道」との内容的隔たりに関することを受講生に対して質問する。その後、その指導の重要性について概説する。その後、その課題に関して出題する(課題研究)。
【事前学習】中学「書写」と高校「書道」との内容的隔たりに関することをノートに書き出す(第5回目の授業中、それについて予告する)。 (2時間) 【事後学習】中学「書写」と高校「書道」との相違について、授業中、取り上げた個々の文字を中心に整理し、その類例を書き出しておく。 (2時間) |
| 7 |
第4・5回目の授業内容、理解度のための確認テストを実施。その後、その解説を行いながら解答する。
【事前学習】第4・5回目の授業内容について各自、内容確認を行っておく。 (2時間) 【事後学習】確認テストの解答・解説について復習を行う。 (2時間) |
| 8 |
表現領域(漢字仮名交じりの書)における指導内容・評価方法について解説する。『粘葉本和漢朗詠集』を取り上げる。評価では「思考力、表現力、判断力」に重きを置く。
【事前学習】『高等学校学習指導要領解説 芸術編』P271~279を通読。表現領域における指導内容・評価方法について理解する。 (2時間) 【事後学習】漢字仮名交じりの書における指導内容・評価方法について、自身の考えをまとめておく。 (2時間) |
| 9 |
表現領域(漢字の書)における指導内容・評価方法について解説する。楷書を取り上げる。評価では「知識・技能」に重きを置く。
【事前学習】『高等学校学習指導要領解説 芸術編』P280~286を通読。配信データ「背勢と向勢」記載内容を理解する。 (2時間) 【事後学習】「背勢と向勢」を教材とし、現場の実際を踏まえ、指導内容・評価方法について自身の考えをまとめておく。 (2時間) |
| 10 |
表現領域(仮名の書)における指導内容・評価方法について解説する。『寸松庵色紙』を取り上げる。評価では「知識・技能」に重きを置く。
【事前学習】『高等学校学習指導要領解説 芸術編』P286~292を通読。配信データ「寸松庵色紙」記載内容を理解する。 (2時間) 【事後学習】「寸松庵色紙」を教材とし、現場の実際を踏まえ、指導内容・評価方法について自身の考えをまとめておく。 (2時間) |
| 11 |
鑑賞領域(漢字の書・仮名の書)における指導内容・評価方法について解説する。書体の変遷、仮名の成立等に関する事項を取り上げる。効果的教材の活用、及び生徒の学習状況を把握するための評価方法について考える(課題研究)。
【事前学習】配信データ「書体の変遷」・「仮名の成立と発達」記載内容を理解する。 (1時間) 【事後学習】「書体の変遷」に関する効果的教材の活用、生徒の学習状況を把握するための評価方法について内容整理を行う。 (3時間) |
| 12 |
書写・書道教育現場の実際と諸問題について質問し、その後、解説を行う。以下、数回に亘り、授業実践への展開に向けて、学習指導案の作成を試みる。オンライン(Zoom)上、その方法と留意点について解説を行う。 その上で学習指導案作成のための課題選びを各自行う(課題研究)。
【事前学習】漢字・仮名の授業における場面をいくつか想定し、現場の実際についてノートに思うところを述べる(第9回目辺りに、それについて予告する)。 (2時間) 【事後学習】授業中、知り得た課題をノートに書き出し、その課題克服のために行うべきこと、授業展開の方法について自身の考えをまとめておく。 (2時間) |
| 13 |
前回に引き続き、学習指導案の作成方法とその留意点について解説を行う。内容確認を行った上で前回に続き、学習指導案の作成を試みる。その際、教材の内容、及びその活用方法について検討を行う(課題研究)。
【事前学習】データ(中国の書に関する)の実例に目を通し、生徒の立場で実際にワークシートを行う。 (1時間) 【事後学習】データ(中国の書に関する)の実例の内容、及び活用方法について再検討を行う。 (3時間) |
| 14 |
前回に引き続き、学習指導案の作成に関する確認を行う。その際、ICT活用の方法・効果について検討を行う。 授業中、学習指導案を提出する。
【事前学習】データ(ICT活用の実例)に目を通しておく。 (3時間) 【事後学習】学習効果が得られると考えられる ICT活用の事例を各自、収集し、後日、提出のこと(他教科、可)。 (1時間) |
| 15 |
既に受講生が作成した学習指導案の検討、相互批評会を全員で行う。全員の指導案について意見を出し合い、それぞれ良い点、改善すべき点を明確にする。一連の作業を通して、『学習指導要領』が示す目標、内容、評価方法について理解を深める。
【事前学習】事前に送信する受講生作成の学習指導案(全員分)を検討し、自身の意見(良い点、改善すべき点)をノートに書き出し、当日答えられるようにしておく。 (2時間) 【事後学習】試験内容、及び学習指導案について、不十分な点があればノートに整理しておく。また、授業中、使用した資料、ノートを読み返し、これまでの学習内容について復習を行う。 (2時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 關正人ほか著 『書Ⅰ』 教育図書 2016年 「306」で特定することができます。 |
| 参考書 | 『中学校学習指導要領』(平成29年 文部科学省) 『高等学校学習指導要領』(平成30年 文部科学省) |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート:テーマに対する内容、提出状況を見て評価します(60%)、授業参画度:授業への取り組み方、成果物等で評価します(40%) |
| オフィスアワー | Zoomによるオンライン授業後、及びE-mailにて受け付けます。 |
| 備考 | ・講義・課題に関することは、毎回の授業前に配信するデータによってご確認下さい。 ・一定期間経過後のデータは順次削除します。ご注意下さい。 ・第1回目のZoomによるオンライン授業に参加できなかった場合は当日の20時までにE-mailにてご連絡下さい。個別対応を行います。 ・「書道科教育法Ⅰ」・「書道科教育法Ⅱ」両科目を履修希望の場合、履修順序は「書道科教育法Ⅰ」→「書道科教育法Ⅱ」とすること。それが不可能な場合は第1回目までにE-mailにてご相談下さい。 |