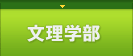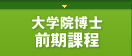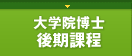検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

論理と計算
| 令和元年度以前入学者 | 論理と計算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度以前入学者 | 論理と計算2 | ||||
| 教員名 | 尾崎知伸 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 情報科学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業の形態 | オンライン同時双方向型(Zoomによるライブ中継) + 一部課題研究(Blackboardを通じた学習資料配信) BlackboardコースID : 水5限→20213034 |
|---|---|
| 授業概要 | 命題・述語論理を対象に,論理に基づく知識の表現と推論の基礎事項について概観する.構文論と意味論に続き,推論手続きについて言及する.また発展として,論理プログラミングとそれに基づく高次推論を取り上げる. |
| 授業のねらい・到達目標 | 命題論理・述語論理を用いた対象の表現と推論の仕組みを理解する. また論理や推論を用いた問題解決の発展について,技術的な側面から検討することができる. この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシーDP6及びカリキュラムポリシーCP9に対応している. |
| 授業の方法 | 授業の形式:【講義】 電子資料を用いた講義形式を中心とするが,随時,演習も行う. 提出されたレポートについては,総評を行う. |
| 履修条件 | 「離散数学」を履修していることが望ましい |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス(授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する) 論理を用いた問題解決の概要 【事前学習】シラバスを事前に確認し, 当該分野に関する簡単な調査を行う (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,論理を用いた対象の表現・推論と問題解決の概要を理解する (2時間) |
| 2 |
命題論理:構文・意味・解釈
【事前学習】命題論理に関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,命題論理の構文や意味,解釈について説明できるようにする (2時間) |
| 3 |
命題論理:標準形・推論
【事前学習】命題論理に関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,命題論理式を標準形へと変換できるようにする.また,推論手続きを説明できるようにする (2時間) |
| 4 |
命題論理:充足可能性問題
【事前学習】充足可能性問題に関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,種々の充足可能性問題の概要を説明できるようにする (2時間) |
| 5 |
命題論理:振り返りと演習
【事前学習】第2~4回の内容を中心に復習を行う (2時間) 【事後学習】第2~4回の内容を中心とした演習問題に取り組む (2時間) |
| 6 |
述語論理:構文・意味・解釈
【事前学習】述語論理に関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,述語論理の構文や意味,解釈について説明できるようにする (2時間) |
| 7 |
述語論理:標準形・推論
【事前学習】述語論理に関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,述語論理式を標準形へと変換できるようにする.また,融合法について説明できるようにする (2時間) |
| 8 |
述語論理:論理プログラムの基礎
【事前学習】論理プログラムに関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,論理プログラムの概要を理解する (2時間) |
| 9 |
述語論理:論理プログラムの発展
【事前学習】論理プログラムに関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,論理プログラムによる対象の表現と問題解決の概要を理解する (2時間) |
| 10 |
述語論理:振り返りと演習
【事前学習】第6~9回の内容を中心に復習を行う (2時間) 【事後学習】第6~9回の内容を中心とした演習問題に取り組む (2時間) |
| 11 |
高次推論:発想推論
【事前学習】発想推論・発想論理プログラムに関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,発想推論の概要を理解する (2時間) |
| 12 |
高次推論:帰納推論の基礎
【事前学習】帰納推論に関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,帰納推論の概要を理解する (2時間) |
| 13 |
高次推論:帰納推論の発展
【事前学習】帰納論理プログラミングに関する配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】授業内容を振り返り,帰納論理プログラミングによる対象の表現と問題解決の概要を理解する (2時間) |
| 14 |
高次推論:振り返りと演習
【事前学習】第11~13回の内容を中心に復習を行う (2時間) 【事後学習】第11~13回の内容を中心とした演習問題に取り組む (2時間) |
| 15 |
まとめと発展的話題
【事前学習】第1~14回までの配布資料を通読し,内容を簡単にまとめる (2時間) 【事後学習】これまでの学修内容を振り返り,どの様な発展が考えられるか考察する (2時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 古川康一,向井国昭 『数理論理学』 コロナ社 2008年 S.J.Russell (著), P.Norvig (著), 古川康一 (翻訳) 『エージェントアプローチ人工知能』 共立出版 2008年 第2版 必要に応じて,解説論文等を紹介・利用する. |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート:授業内容の振り返りを中心とし,内容の正しさと理解度合を中心に評価をする.(85%)、授業参画度:講義中に行う実習・演習の成果により評価する.(15%) |
| オフィスアワー | 質問等は随時を受け付ける.原則,事前にメール等でアポイントをとること |