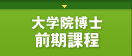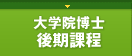検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

権利擁護と成年後見制度2
| 平成28年度以前入学者 | 権利擁護と成年後見制度2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 山本 克司 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 集中 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 権利擁護にかかわる法制度、成年後見制度、日常生活自立支援事業および権利擁護活動の実際を理解する。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 人権尊重と現実的な個人の尊厳保障は、社会福祉の究極の目的である。現代社会において、DV、児童、障がい者、高齢者への虐待とともに、認知症、老老介護、介護殺人、社会的排除等権利擁護の重要性は増すばかりであり、取り組むべき重要な課題となっている。本講義では、基本的人権の理解を中核にして、権利擁護の基本的理解を深めると共に、社会福祉士として、背景と課題を科学的に把握、分析した上で権利擁護活動の具体的実践を学ぶ。「権利擁護と成年後見制度2」においては、「権利擁護と成年後見制度1」で学んだ基本的人権と法学の基礎知識を現実の課題の中で発展させるとともに、成年後見制度、日常生活自立支援事業、権利擁護を担う社会福祉士の役割と活動、権利擁護活動の実際について理解する。 |
| 授業の方法 | 授業は講義形式で進めるが、より実践的な理解を深めるため演習を行う場合がある。社会福祉士国家試験科目であるため、単元ごとに過去問を利用した知識の整理を行うことがある。 |
| 履修条件 | 社会福祉士国家試験科目です。社会福祉士を目指す学生は可能な限り選択することがのぞまれます。「権利擁護と成年後見制度1」と「権利擁護と成年後見制度2」で1つの体系となっていますから、「権利擁護と成年後見制度1」受講後に、「権利擁護と成年後見制度2」を選択してください。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 専門的な科目であり、可能な限り「高齢者福祉論1・2」を選択しておくことがのぞましく、もしくは、同等の学習をしておいてください。 「権利擁護と成年後見制度1」と「権利擁護と成年後見制度2」で1つの体系となっています。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ふりかえり―権利擁護(アドボカシー)とは何か |
| 2 | 成年後見制度創設の背景と成年後見制度の趣旨 |
| 3 | 法定後見制度の概要(1)成年後見の概要 |
| 4 | 法定後見制度の概要(2)保佐の概要、補助の概要 |
| 5 | 任意後見制度の概要 |
| 6 | 日常生活自立支援事業の創設の背景と制度のしくみ |
| 7 | 日常生活自立支援事業における支援の概要と支援の実際 |
| 8 | 権利擁護を担う社会福祉士の役割と活動 |
| 9 | 権利擁護活動の実際(1)認知症を有する者への支援の実際 |
| 10 | 権利擁護活動の実際(2)高齢者虐待防止への支援の実際 |
| 11 | 権利擁護活動の実際(3)消費者被害を受けた者への支援の実際 |
| 12 | 権利擁護活動の実際(4)障がい児・者への支援の実際 |
| 13 | 権利擁護活動の実際(5)精神障がい者への支援の実際 |
| 14 | 社会的排除―格差社会、貧困、ワーキングプア、ホームレス、「孤独死」、「孤立死」、「無縁社会」等 |
| 15 | 権利擁護活動の事例研究 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 山口光治 『権利擁護と成年後見制度』 みらい 2016年 第3版 |
| 参考書 | 授業中に適宜指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(40%)、レポート(40%)、授業参画度(20%) |
| オフィスアワー | 授業終了時。 |
| 備考 | 社会福祉士国家試験科目である。授業中の私語、テキストを忘れる等、授業態度に課題がある場合は、厳重注意を行う。 |