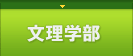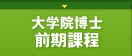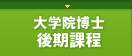検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

教育の方法・技術論
| 科目名 | 教育の方法・技術論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 田村 恵美 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 半期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 教育方法の理論と実践、教育方法の歴史、専門家としての教師 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 本講義の目的は、教育方法の基礎的な知識と技術を習得することである。近年の学校教育をめぐる様々な教育課題を踏まえたうえで、日本をはじめ先進諸国における教育方法の理論と歴史の理解を深めることを目指す。また、授業実践の事例を参考にしながら、教育の目的に適した基礎的な指導技術を学ぶことにより、地域の実情や子どもの興味・関心に即した授業を行えるための実践力を身に付ける。 本講義の到達目標は、次の三点である。 1.教育方法に関する基礎的な理論と歴史を説明することができる。 2.学校教育をめぐる諸課題を踏まえた上で、学習指導要領に基づきながら、適切な教育方法を用いることができる。 3.専門職としての教師という立場から様々な教育実践の原理や指導技術を理解し、実践することができる。 |
| 授業の方法 | 1.基本的には講義形式で行うが、受講者数に応じてグループワーク、ディスカッションを行う。 2.第7回、第8回の「諸外国の教育方法」では受講者に問題解決学習を進めてもらい、発表を課す。初回の講義で、発表に関するガイダンスを行うため、初回を欠席する場合は、tamura.class@gmail.comまで必ず連絡をすること。連絡がなく欠席したの場合、履修を認めないこともあるため注意すること。 3.多様な教育実践があることを理解し、自身のこれまでの教育経験を相対化することを目指すことから、テーマに関連のある授業実践の映像資料を用いての講義も行う。 4.講義の計画は、受講者の関心や理解度などに応じて、適宜トピックや講義の順序を変更することがある。 |
| 履修条件 | 本講義は教職に関わる科目であることから、遅刻や欠席には厳しい。また、受講態度も評価対象とするため、講義への積極的な参加を期待する。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業計画を参考に、次回取り扱うコンテンツに関する参考文献等を読む。 講義後には毎時間リアクションペーパーを課すため、必ず提出すること。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス―本講義の進め方や評価方法などの全体的な説明、教育方法学の固有性 |
| 2 | 学習指導要領の変遷と現在の教育課題 |
| 3 | 教育方法の理論と歴史(1)戦前における教育方法 |
| 4 | 教育方法の理論と歴史(2)戦後における教育方法 |
| 5 | 日本の教育方法(1)学力論争の視点から「総合学習」の実践を考える |
| 6 | 日本の教育方法(2)学習環境の視点から「オープンスクール」の実践を考える |
| 7 | 諸外国の教育方法(1)アメリカ・イギリス |
| 8 | 諸外国の教育方法(2)フランス・ドイツ |
| 9 | 授業分析の理論と方法 |
| 10 | 優れた授業に学ぶ(1)授業分析:主体的・対話的で深い学びの観点から |
| 11 | 優れた授業に学ぶ(2)授業分析:発問・板書の技術、情報機器の活用 |
| 12 | 教育評価の理論と方法 |
| 13 | 中間まとめと学びの省察 |
| 14 | 主体的な学びの意義と方法論 |
| 15 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 文部科学省 『中学校学習指導要領解説 総則編』 (平成29年3月告示 文部科学省) 文部科学省 『高等学校学習指導要領解説 総則編』 (平成30年度改訂予定のもの 文部科学省) |
| 参考書 | 授業中に適宜資料を配付する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(60%)、授業参画度(40%) 授業参画度には、受講態度・リアクションペーパー・発表などを含む。 |
| オフィスアワー | 講義終了時 |