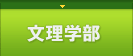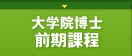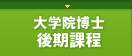検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

古文書・古記録学2
| 科目名 | 古文書・古記録学2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 千葉 篤志 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 室町~戦国時代の古文書・古記録を読む |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 日本中世史の中でも室町・戦国時代の古文書と古記録の講読を通じて、卒業論文作成に必須となる史料の読解力を身に付けることを目的とする。基本的に史料の講読を中心に授業を進めるが、本授業では、史料の形状や花押など、特に史料の様式にも触れ、室町・戦国時代の史料への理解を深める。 |
| 授業の方法 | 基本的にプリントを配布して進める。史料の音読や板書など、史料への理解をより深める作業をする場合もある。基本的に文書の形式ごとに授業を進めるが、古文書の基本的な読み方や史料集の見方など、史料の読解に当たって必要な調査方法にも言及していく。また、授業期間中に課題レポートを提出してもらう。 |
| 履修条件 | 熱意と真摯な態度を持っていれば受講資格は問わないが(必ずしも単位の取得を保証するわけではない)、史料への理解をより深めるため、前期の古文書・古記録学1を受講していることが望ましい。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業では、室町時代から戦国時代を中心に取り扱うが、内容により織田政権・豊臣政権時代を扱う場合もある。また、授業の受講人数・進捗状況によって授業の進め方(史料の音読など)を変更する。また、図書館での調査や博物館の古文書の展示など、すぐに理解できなくても、時間がある時に史料に触れる機会を作ることを推奨する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス(授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する) |
| 2 | 室町幕府の下文・下知状 |
| 3 | 御判御教書 |
| 4 | 施行状・遵行状・打渡状 |
| 5 | 軍忠状・感状 |
| 6 | 一揆契状 |
| 7 | 起請文 |
| 8 | 直状・書下 |
| 9 | 印判状 |
| 10 | 戦国大名の書状1(東国) |
| 11 | 戦国大名の書状2(西国) |
| 12 | 戦国時代に関する史料(覚書・棟札など) |
| 13 | 中世後期の古記録1(室町時代) |
| 14 | 中世後期の古記録2(戦国時代) |
| 15 | 授業内試験と総括 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 佐藤進一 『[新版]古文書学入門』 法政大学出版局 2003年 |
| 参考書 | 山田邦明 『戦国のコミュニケーション (歴史文化セレクション)』 吉川弘文館 2011年 酒井紀美 『戦乱の中の情報伝達 (歴史文化ライブラリー372)』 2014年 古文書読解にあたって、漢和辞典や『日本国語大辞典』(小学館)など、辞典類の活用を推奨する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(20%)、授業内テスト(20%)、授業参画度(60%) |
| オフィスアワー | 授業終了後に史学科事務室または講師室 |
| 備考 | 史料講読は地道な作業の連続である。ただ、この地道な道程こそが、古文書の読解力の養成の近道である。早い段階からの着手を推奨する。 |