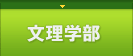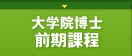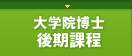検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

社会学演習1
| 平成28年度以降入学者 | 社会学演習1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 山本 質素 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 社会学の基本的な考え方・概念・用語・方法を理解する |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 社会学の基本概念・用語・研究法を整理し、現代社会の出来事を理解するための社会学的な視点を身につけ、理解に至る思考過程を表現する基礎的な力を身につける |
| 授業の方法 | 演習形式。教材を輪読し、文意を理解する過程で抽出した概念・用語・定義等とその用法を整理・検討する 1)次の3つの過程を反復して学習する。①テキストの輪読・文意の理解と重要語句・概念の抽出、②用語・概念の整理・検討、③用語・概念からの展開・活用 2)演習発表者は次の内容を整理し、レジュメを作成する (1)教材担当箇所の理解と要約、(2)用語・概念・キーワード等の内容提示(『社会学事典』等を参照)、(3)補足資料、(4)課題の展開・応用 3)演習発表者は、レジュメに基づいて発表し、質疑応答を行う |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | ①演習発表担当者の事前学習:教材文献を読解し、『社会学事典』等を活用してレジュメを作成する。レジュメ作成の過程で、引用・出典表記・注の付け方等の作法(技術)を習得する。演習発表の準備を行う ②発表者の事後学習:発表と質疑応答の内容を確認し、レジュメの整理を行う ③発表者以外の事前学習:事前に配付されたレジュメを熟読し、疑問点・課題を整理する ④発表者以外の事後学習:配付資料(レジュメ等)の再読・質疑応答の内容確認を行う |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 演習の目的と授業形式の説明 |
| 2 | 講義:レジュメによる講義:レジュメ作成の作法等 |
| 3 | 演習:教材(社会学の歴史1 西欧社会の社会学史 1「社会」という謎の発見、ほか)の輪読、および、用語・概念の抽出 |
| 4 | 演習発表1・質疑応答 |
| 5 | 演習:教材(社会学の歴史1 西欧社会の社会学史 2「理性」からはみ出る社会、ほか)の輪読、および用語・概念の抽出 |
| 6 | 演習発表2・質疑応答 |
| 7 | 演習:教材(社会学の歴史1 西欧社会の社会学史 3「アメリカ社会学」はいかに可能か、ほか)の輪読、および用語・概念の抽出 |
| 8 | 演習発表3・質疑応答 |
| 9 | 中間のまとめ |
| 10 | 演習:教材(社会学の歴史1 西欧社会の社会学史 4「わからなさ」の再発見、ほか)の輪読、および用語・概念の抽出 |
| 11 | 演習発表4・質疑応答 |
| 12 | 演習:教材(社会学の歴史1 西欧社会の社会学史 5神なき時代の社会学、ほか)の輪読、および用語・概念の抽出 |
| 13 | 演習発表5・質疑応答 |
| 14 | 第2回目から第13回目までの講義内容について質疑応答を行う。 |
| 15 | まとめと夏季課題の確認 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 宇都宮京子編 『よくわかる社会学 [第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)』 ミネルヴァ書房 2009年 第2版 |
| 参考書 | 授業の進展にあわせて紹介する |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業参画度(50%) レポートはレジュメの作成と提出(発表の前週に提出) 授業参画度の評価は、「演習発表と質疑応答」時の態度・内容を含む 夏季課題を課す(夏季課題は社会学演習2で評価する) |
| オフィスアワー | 開講時に指示する |