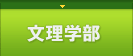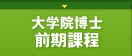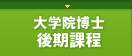検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

社会学概論2
| 科目名 平成28年度以降入学者 |
社会学概論2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 木下 征彦 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 現代社会を社会学的に分析するための視点と方法を学ぶ。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 社会学とは、人と人の関係という視点から、社会を実証的に分析して説明する学問である。 この授業では、社会学の概念と命題を用いて現代社会を分析するための基本的な視点と方法を修得することを目的とする。 そのため、教育現場や職場など、現実社会のさまざまな場面で役立つ現代社会の多様な領域についての社会学的知識を学修する。 |
| 授業の方法 | 講義形式 |
| 履修条件 | 主に教職コース履修者(「社会学概論1」を履修済みであることが望ましい) |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学修として、毎回の授業前に教科書の該当部分を予習して、社会学的な視点と方法に触れておくこと。また、現実社会の事件や出来事を授業内で取り上げ、社会学的に考えるケーススタディを行うので、日ごろから新聞やニュースに触れておくことが望ましい。 事後学修として、専門用語に慣れるため、授業ノート・プリントを復習して、授業で取り上げた社会学的な理論や概念についての理解を深めること。 授業では、社会学を初めて学ぶ学生が無理なく内容を理解することを目指して対話型講義によるケーススタディを行う。受講生の積極的な発言や参加を期待する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス(授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する) [準備]シラバスの内容を事前に確認すること |
| 2 |
現代社会と社会学 ―― 社会学的分析のケーススタディ [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 3 |
社会学的分析の視点と方法 ―― 科学としての社会学 [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 4 |
家族の社会学(1)―― 人はなぜ家族をつくるのか [準備]教科書第5章を読んでおくこと |
| 5 |
家族の社会学(2)―― 家族のあり方の現在(いま)を問う [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 6 |
地域の社会学(1)―― コミュニティとは何か [準備]教科書第7章を読んでおくこと |
| 7 |
地域の社会学(2)―― 都市化と地域社会の変容 [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 8 |
産業と組織の社会学(1)―― 豊かな社会のメカニズム [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 9 |
産業と組織の社会学(2)―― 人は組織とどう向き合うのか [準備]教科書第2章を読んでおくこと |
| 10 | 中間まとめ/授業内小テスト |
| 11 |
階級と階層 ―― 持てる者と持たざる者のメカニズム [準備]教科書第4章を読んでおくこと |
| 12 |
消費社会と環境問題 ―― 市場原理主義を超えて [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 13 |
国民国家とグローバル化 ―― 民族とナショナリズムの先に [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 14 |
メディアと社会 ―― 世論から考える [準備]前回配付資料を読んでおくこと |
| 15 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 夏刈康男・松岡雅裕・杉谷武信・木下征彦 『行為、構造、文化の社会学』 学文社 2011年 第1版 |
| 参考書 | 適宜指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(70%)、授業内テスト(15%)、授業参画度(15%) 授業参画度には、出席点・小レポート等を含む。 |
| オフィスアワー | 授業終了時。 |
| 備考 | この授業は、「社会学概論1」で取り扱うの社会学の基本的な考え方と概念を修得していることを前提として展開する。そのため、受講者はすでに「社会学概論1」を履修済みであることが望ましい。 |