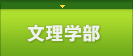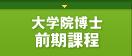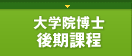検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

物理の基礎2
| 平成28年度以降入学者 | 物理の基礎2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 基礎物理 | ||||
| 教員名 | 石田浩 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 物理学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業概要 | 物理学の方法と考え方を学ぶ |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 「物理の基礎1」に続き、物理の専門科目を学ぶ上で必要になる基礎知識を身につける。 この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシーDP6及びカリキュラムポリシーCP9に対応している。 |
| 授業の方法 | 通常の講義形式により行う。 本授業の事前・事後学習は、各2時間の学習を目安とします。 |
| 履修条件 | なし |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
2次元直交座標と座標系の回転・鏡映1(2x2の直交行列を使って座標系の関係を表す、2x2行列の行列式、逆行列の計算を学ぶ) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 2 |
2次元直交座標と座標系の回転・鏡映2(2x2の直交行列を使って座標系の関係を表す、2x2行列の行列式、逆行列の計算を学ぶ) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 3 |
3次元直交座標系と座標系の回転(3x3の直交行列を使って2つの座標系の関係を表す、3x3の行列式、逆行列の計算を学ぶ) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 4 |
3次元直交座標系と座標系の反転・鏡映(3x3の直交行列を使って2つの座標系の関係を表す、3x3の行列式、逆行列の計算を学ぶ) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 5 |
座標系の変換と物理量:スカラー 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 6 |
座標系の変換と物理量:極性ベクトルと軸性ベクトル(磁場は普通のベクトルか?) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 7 |
座標系の変換と物理量:ベクトルの内積とベクトル積(外積) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 8 |
座標系の変換と物理法則の不変性(物理法則は空間反転で不変でない?) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 9 |
スカラーポテンシャル、勾配、発散、回転1(微分積分2で学んだ偏微分をつかって、勾配・発散・回転がスカラー、ベクトルとして変換することを確かめる) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 10 |
スカラーポテンシャル、勾配、発散、回転2(微分積分2で学んだ偏微分をつかって、勾配・発散・回転がスカラー、ベクトルとして変換することを確かめる) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 11 |
スカラーポテンシャル、勾配、発散、回転3(微分積分2で学んだ偏微分をつかって、勾配・発散・回転がスカラー、ベクトルとして変換することを確かめる) 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 12 |
ガリレイ変換とニュートン方程式 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 13 |
光速不変の原理とローレンツ変換 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 14 |
特殊相対論 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| 15 |
これまでの講義内容の復習・解説を行い授業の理解を深める 【事前学習】 次回テーマに関して参考書等に目を通しておく 【事後学習】 ノートを読み返し、理解不足を補っておくこと |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(70%)、授業参画度(30%) 出席回数が十分でない場合は成績評価の対象としない |
| オフィスアワー | 授業内容に関する質問は授業後あるいは学科事務室で受け付けます。その後、時間を調整して、物理学科図書室または本館1階で応対します。 |