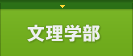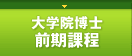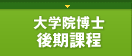検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

現代文学特殊講義4
| 科目名 | 現代文学特殊講義4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 武内佳代 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | 「語り」を捉え直す:アプローチの方法と実践 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 〈作者〉と〈読者〉の相互作用としての〈書く〉ことと〈読む〉ことを捉え返すかたちで、近現代小説の「語り」に関する概念や分析方法を学ぶ。 |
| 授業の方法 | 教員によるイントロダクションの後、文献を読み、議論する。文献は前もって担当を決め、担当者は担当範囲を要約しながら提示し、コメントを付す。 本授業の事前・事後学習は,各2時間の学習を目安とします。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス、作品・スケジュールの決定 【事前学習】教科書を準備し、シラバスを読んでくる 【事後学習】担当個所について熟読する |
| 2 |
「第1章 「物語の構造」とは―プロップからバルトまで」を読む(1)イントロダクション 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 3 |
「第1章 「物語の構造」とは―プロップからバルトまで」を読む(2)ディスカッション 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 4 |
「第2章 ナラトロジー誕生までの理論的背景」を読む 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 5 |
「第3章 「作者」と「語り手」について」を読む 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 6 |
「第4章 物語の「時間」」を読む 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 7 |
「第5章 視点(焦点化)と語る声」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 8 |
「第6章 日本語における焦点化の仕方とオーバーラップ」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 9 |
構造としての語り――イントロダクション 【事前学習】課題書を粗々読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 10 |
「『坊っちやん』の〈語り〉の構造――裏表のある言葉」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 11 |
「『心』での反転する〈手記〉――空白と意味の生成」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 12 |
「『蝿』の映画性――流動する〈記号〉/イメージの生成」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 13 |
「エクリチュールの時空――相対性理論と文学」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 14 |
「文字・身体・象徴交換――流動体としてのテクスト『上海』」 【事前学習】対象頁を読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| 15 |
総括的ディスカッション 【事前学習】課題書を改めて読んでくる 【事後学習】議論を理解できているかを確認する |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 橋本陽介 『ナラトロジー入門―プロップからジュネットまでの物語論』 水声社 2014年 小森陽一 『構造としての語り・増補版』 青弓社 2017年 第増補版 必要に応じて小説テキストは受講生で入手する。 |
| 参考書 | 授業の中で適宜紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(100%) 口頭発表の内容、討論への参加態度、課題である選評内容の評価を授業参画度とする。 |
| オフィスアワー | 水曜4限と木曜3限、7号館4階武内研究室。質問等がある場合は、事前にメールで予約すること。メールアドレスは授業で知らせる。 |