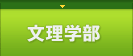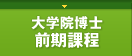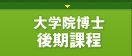検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

微分積分学2(含演習)(再履修)
| 令和2年度入学者 | 微分積分学2(含演習)(再履修) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度以前入学者 | 微分積分学2(含演習)(再履修) | ||||
| 教員名 | 立井博子 | ||||
| 単位数 | 3 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 数学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業の形態 | オンデマンドで行なう。 |
|---|---|
| 授業概要 | 微分,積分の基礎を学ぶ |
| 授業のねらい・到達目標 | きちんとした論理思考ができるようになる。 この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシー DP3, DP6 及びカリキュラムポリシー CP1, CP9 に対応しています。 なお,新カリキュラムにおいては,文理学部(学士(理学))のディプロマポリシー DP3,DP4,DP6,DP8 及びカリキュラムポリシー CP3,CP4,CP6,CP8 に対応しています。 ・数理科学に基づいて学んだ知識をもとに、物事の本質を論理的、客観的に捉えることができる(A-3-2)。 ・日常生活における現象に潜む数理科学的問題を発見し、内容を説明することができる(A-4-2)。 ・周りの人々と相互に意思を伝達することができる(A-6-1)。 ・自分の学修経験の振り返りを継続的に行うことができる(A-8-1)。 |
| 授業の方法 | 授業と演習,毎回,小試験を行う。 事前・事後学習の具体的な内容は授業時間内に伝える。 小試験は採点をして返却をするので、 これについても復習をしておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
オンデマンドで行なう。最大,最小,上限,下限の違いについて学び,その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】シラバスを確認して,授業全体の流れを把握すること。 (2時間) 【事後学習】最大と上限の違いに注意して, 第1回の講義ノートを整理する(A-8)。 (3時間) |
| 2 |
オンデマンドで行なう。εーδ法のまとめ,極限の定義
【事前学習】数学入門で学修した「論理」について復習しておく。 (2時間) 【事後学習】第2回の講義ノートを整理し, εーδ法を身に着ける(A-8)。 (3時間) |
| 3 |
オンデマンドで行なう。積分の定義について学び、その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】前回の講義内容を復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第3回の講義ノートを整理し, 積分の厳密な定義の仕方を理解しておく(A-8)。 (3時間) |
| 4 |
オンデマンドで行なう。積分の定義とその性質について学び、その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】前回の講義内容を復習し、積分の定義を思い出しておく。 (2時間) 【事後学習】第4回の講義ノートを整理し, 積分の基本性質を覚えること。 (3時間) |
| 5 |
オンデマンドで行なう。積分の定義,連続関数の積分の存在について学び、その計算演習を行う(A-3,A-4)。
【事前学習】前2回分の講義内容を復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第5回の講義ノートを整理し, 計算演習を行う(A-8)。 (3時間) |
| 6 |
オンデマンドで行なう。広義積分の定義とその性質について学び、その演習問題を解くこと(A-3, A-4)。
【事前学習】積分の定義及び計算方法について復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第6回の講義ノートを整理し, 極限を用いた広義積分の定義を理解しておくこと(A-8)。 (3時間) |
| 7 |
オンデマンドで行なう。完備性について学び、その演習問題を解くこと。
【事前学習】これまでの学習内容を整理しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第7回の講義ノートを整理すること(A-8)。 (3時間) |
| 8 |
オンデマンドで行なう。初歩の重積分の計算方法を学び、具体的な演習問題を解くこと(A-3,A-4)。
【事前学習】前回の講義内容を復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第8回の講義ノートを整理し(A-8), 簡単な重積分の計算方法を身に着けること。 (3時間) |
| 9 |
オンデマンドで行なう。学習度のチェック,学習の再確認(A-3,A-4)。
【事前学習】1〜8回までの講義内容を復習しておくこと。 (3時間) 【事後学習】友人たちと解けなかった問題について議論し, 解けるようにしておくこと(A-6)。 (2時間) |
| 10 |
オンデマンドで行なう。連続関数の定義について学び、その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】εーδ法と関数とについて, 復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第10回の講義ノートを整理すること(A-8)。 (3時間) |
| 11 |
オンデマンドで行なう。連続関数とその性質について学び、その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】前回の講義内容を復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第10回の講義ノートを整理し, 連続関数の基本性質を理解しておくこと。 (3時間) |
| 12 |
オンデマンドで行なう。一様収束と一様連続性について学び、その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】前回の講義内容を復習しておくこと (2時間) 【事後学習】第11回の講義ノートを整理し, 一様収束と各点収束の違いを理解しておくこと. (3時間) |
| 13 |
オンデマンドで行なう。積分と極限の交換について学び、その演習問題を解く(A-3,A-4)。
【事前学習】前回の講義内容を復習しておくこと。 (2時間) 【事後学習】第12回の講義ノートを整理し, いつ積分が極限と順序交換できるのかを理解しておくこと。 (3時間) |
| 14 |
オンデマンドで行なう。習熟度のチェックと解説(A-3,A-4)。
【事前学習】第13回までの学習内容について復習しておくこと。 (3時間) 【事後学習】友人と解けなかった問題について議論し, 解けるようにしておくこと。 (2時間) |
| 15 |
オンデマンドで行なう。学習の再確認(これまでの講義内容の復習・解説を行い,授業の理解を深める)
【事前学習】授業全般の振り返り (時間) 【事後学習】授業全般を振り返り、整理する(A-8)。 (時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教科書は使用しない。 |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(100%) 成績評価については1回目に説明する. 授業参画度は毎回の演習およびレポート等で評価する. 授業内テストを通して, A-3,A-4の達成度を評価し, 机間指導などを通じて, A-6の達成度を評価する。 また, 事後学修のレポートなどを通じて, A-8の達成度を評価する。 |
| オフィスアワー | 随時受け付ける. |
| 備考 | 学生の理解度により授業は柔軟に対応する |