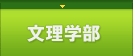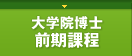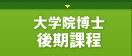検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

司法福祉論
| 令和3年度以降入学者 | 司法福祉論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度以前入学者 | 司法福祉論 | ||||
| 教員名 | 長谷川洋昭 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会福祉学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業の形態 | 対面授業(一部ZOOMによるライブ中継あり) 2021司法福祉論(長谷川洋昭・前・金1) blackboardコースID→20221015 |
|---|---|
| 授業概要 | 洋の東西を問わず、「犯罪」を取り扱うニュースやエピソードは人々の耳目を集める。名探偵が犯人を突き止める推理小説、刑事が犯人を追いつめるテレビドラマ。しかし、これらは犯人が捕まった「その後」は描かれていないものが大半である。また現実社会でも、事件の概要や裁判・判決については詳細に報じられるものの、犯人の「その後」はほとんど知りえることはない。罪を犯した者の生活暦を辿ると、「貧困」「無知」「疾病(これは高齢含む)」などといった、いわゆる支援を必要とする要素が示されることが多い。この分野についての学びを深めることは、様々な網の目からこぼれ落ちた人々の存在を認識することにもつながるといえる。社会福祉士・精神保健福祉士たる法務省保護司として、理論と実践を時事を絡めながら教授していく。 |
| 授業のねらい・到達目標 | 本講義ではソーシャル・インクルージョンの視点から、更生保護制度の現状と課題を把握することを目標とする。犯罪者や非行少年の「更生」だけでなく、そもそも犯罪そのものが起きにくい社会創りを考えることができる。 ・相談援助活動において必要となる更生保護制度について理解することができる。(Aー1-3) ・更生保護を中心に、刑事司法・少年司法分野で活動する組織、団体及び専門職について理解することができる。(A―4-3) ・刑事司法・少年司法分野の他機関等との連携の在り方について理解することができる。(A―3-3) この科目は文理学部(学士(社会福祉学)のDP及びCPの6,8に対応しています。 |
| 授業の方法 | 授業の形式【講義】 レジュメを毎回配布するので、それを閉じるファイルを用意すること。 授業内で提出した課題・リアクションペーパーなどは、授業において適宜フィードバックし、ポイントについて解説する。 ※以下の要件を満たす学生はzoomでの参加を認める場合がある。 ・zoomでの参加を認める要件:日本に入国できない留学生、遠方に居住している学生。 ※対面授業に参加できない場合は、zoomで参加し、Blackboardに配信する課題を提出する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス・更生保護の理念と目的(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3)
【事前学習】そもそも「犯罪とは何か」、を自分なりに整理する。 (1.5時間) 【事後学習】「犯罪」と「更生」について配布物、板書を読み直すこと。 (2.5時間) |
| 2 |
更生保護のあらまし(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.更生保護と刑事司法・少年司法 2.更生保護と司法福祉・社会福祉 【事前学習】「非行少年」の定義について概要を整理する。 (2時間) 【事後学習】犯罪白書の該当部分にあたること。 (2時間) |
| 3 |
更生保護の制度①(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.仮釈放 2.生活環境調整 3.保護観察 【事前学習】仮釈放の存在意義について自分なりに整理する。 (2時間) 【事後学習】生活環境の課題ついて具体的に整理する。 (2時間) |
| 4 |
更生保護の制度②(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 4.更生緊急保護 5.恩赦 6.被害者支援 7.更生保護における犯罪予防活動 【事前学習】保護観察制度から外れる人を整理する。 (2時間) 【事後学習】自らが居住する地域の「社会を明るくする運動」について整理する。 (2時間) |
| 5 |
視聴覚教材「犯罪を犯した人の地域生活支援」 (Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3)
【事前学習】知的障害や高齢など、生活上に課題を持つ人の存在を整理する。 (2時間) 【事後学習】自らが居住する地域の社会資源について整理する。 (2時間) |
| 6 |
更生保護の担い手(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.保護観察官 2.保護司 3.社会復帰調整官 【事前学習】自らが居住する地域の民生委員・保護司について整理する。 (2時間) 【事後学習】メディアが取り上げた保護司制度について複数調べ課題を整理する。 (2時間) |
| 7 |
更生保護の担い手②(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.更生保護施設 2.民間協力者(BBS会・協力雇用主、自立準備ホーム等) 【事前学習】都内における更生保護施設について整理する。 (2時間) 【事後学習】いわゆる特例子会社や障碍者の「就労支援サービス」について整理する。 (2時間) |
| 8 |
関係団体・機関との連携・協力(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.矯正施設との連携・協力 2.検察庁との連携・協力 3.裁判所との連携・協力 4.社会福祉・医療機関・団体との連携・協力 【事前学習】犯罪白書等で関係団体等の存在を概観する。 (2時間) 【事後学習】海外の矯正施設内での教育について複数の事例を調べる。 (2時間) |
| 9 |
関係団体・機関との連携・協力②(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.就労支援機関との連携・協力 2.学校との連携・協力 3.その他の機関・団体との連携・協力 【事前学習】一般的な就労支援サービスを整理する。 (2時間) 【事後学習】社会福祉協議会やボランティアの取組みについて調べる。 (2時間) |
| 10 |
視聴覚教材「累犯知的障碍者の地域生活支援」(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3)
【事前学習】知的障害の特性について整理する。 (2時間) 【事後学習】地域生活定着支援センターの具体的活動をネットにて収集し整理する。 (2時間) |
| 11 |
医療観察制度の概要(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.生活環境調査 2.生活環境調整 【事前学習】精神障害の特性について整理する。 (2時間) 【事後学習】地方裁判所における審判の流れを関係者とともに再度整理する。 (2時間) |
| 12 |
医療観察制度の概要(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3) 1.精神保健観察 2.関係機関・団体との連携 【事前学習】保護観察制度の流れについて再度把握する。 (2時間) 【事後学習】医療観察法制定にいたる世論について整理する。 (2時間) |
| 13 |
更生保護分野における事例検討(就労支援を中心に)(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3)
【事前学習】我が国における産業構造を概観する。 (2時間) 【事後学習】さまざまな背景を持つ対象者に対する情報提供の現状を整理する。 (2時間) |
| 14 |
更生保護分野における事例検討(薬物事犯者を中心に)(Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3)
【事前学習】薬物犯罪の現況を整理する。 (2時間) 【事後学習】依存症治療の施設や回復プログラムを整理する。 (2時間) |
| 15 |
まとめ(更生保護分野において期待される社会福祉士の役割) (Aー1-3)(A―4-3)(A―3-3)
【事前学習】更生保護分野で活動している社会福祉士の役割を整理する。 (1時間) 【事後学習】社会福祉士の立場での限界と、開発すべき事柄について多面的に考える。 (3時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート:求めるテーマと内容、提出状況等を勘案します。フィードバックで総評します。(60%)、授業参画度:リアクションペーパー等の提出物(30%)、積極的発言など受講姿勢(10%) 対面授業に参加できない場合の要件を満たし、zoomで参加した場合、課題の提出によって評価する。 |
| オフィスアワー | 講義終了時に各自と調整する。 |